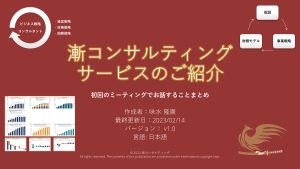【集中講座2の小話】なぜ金融業界や資本市場の構造を知っておいた方が良いのか?
皆さま、こんにちは
先日、金融業界のキープレイヤーやキャリアパス、そして資本市場に関する集中講座をYouTubeに掲載しましたので、今回はその小話として、なぜそれらを知っておいた方が良いのかを考察してみます。
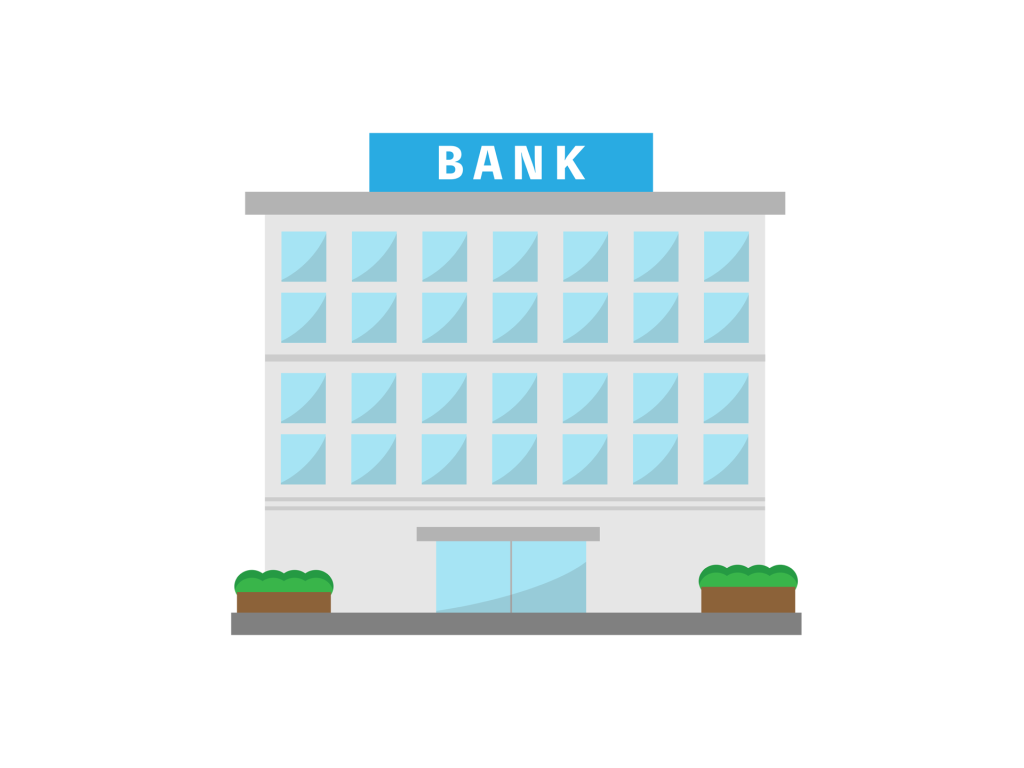

1.需要のあるビジネスを一早く知る事ができる
一つ目の知っておいた方が良い理由は、業界や市場を把握する事で、現在または近い将来需要のあるビジネスを知る事が出来るからです。人がどのようなサービス・商品に関心を持っているのか、リアルタイムで情報を得やすくなります。
例えば、ある業種に新規参入者が急激に増えていたり、特定の株式・先物が買われていたり、または合併・買収が進んでいる業界があると分かれば、何らかの需要がそこに存在する可能性があります。
具体例を挙げますと、コロナパンデミックが起きて以降の数年間、特に欧米を中心として各国政府は、救済策として自国民にお金をばら撒きました。しかし、お金をばら撒きすぎた結果、その余って行き所の無くなった資金が、テレワークや巣篭もり需要を満たすためのフィンテック・IT業界へと流れます。
投資を行っている方であればご存知の事と思うのですが、2021年から2022年にかけて、実際それら関連企業では増収となり、株価も右肩上がりで上昇し続けました。
このように、金融やマーケットに関心を持っている人たちは皆、最新情報には敏感なので、うまく情報を分析して行動に移せば、次のビジネスムーブメントを一早く捉える事ができます。
2.リスクを把握する事で、将来の需要をある程度予測する事ができる
それと、需要が把握できるという事は、将来起こりうるリスクもある程度は予測可能という事になります。
例えば、現在はAI関連のビジネスが活況を呈しており、AI導入のメリットだけではなく、将来予測されるリスクにも言及されるようになっています。確かに、既存ビジネスの多くがAIによって代替される事は、ほぼ確定事項と思った方が良いでしょう。
ただそうなれば、当然そこから新たなビジネス需要も生まれてくるはずです。効率的にAIから情報を引き出すためのプロンプターや、AIが出力する内容の妥当性を検証するための人材などは、既存サービスではすぐにニーズを満たせないので、間もなく出てくると思います。(すでにあっても不思議ではありませんが)
他の事例では、2023年に入ってからはポストコロナの動きが社会全体で進み、政府もこれまでは「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていたものを、5月8日付けで「5類感染症」としました。つまり、法律に基づいて行政が積極的に関与していく方針から、個人の選択を尊重し、国民の自主的な取り組みをベースにした対応に変わったという事です。
政府の決定もあってか、最近はマスクを付けない人も増えていますし、その結果テレワークや巣篭もり需要も少なくなりました。したがって、スマホやPCなどの製造に必要となる半導体製品の需要も少なくなり、一部の半導体業界やIT業界は苦境に立たされています。
加えて、欧米各国での過度な物価高(インフレ)を抑制するために、今年の初めごろに米国で金利が引き上げられました。その決定に対して市場はすぐに反応し、フィンテックやIT産業への投資意欲が薄らいで、株価は暴落する事になります。
このように、それら関連企業の業績・株価が軒並み落ち込んでいる状況(リスク)を鑑みれば、自宅でのテレワークからオフィス回帰への傾向が読み取れるので、現場オフィス関連の商品やサービスの需要回復は当然予想できます。そしてプライベートであれば、今まで自宅中心で暮らしていた人が外出しだすので、旅行・アウトドア・外食等の需要が急激に回復するのも想像できるでしょう。
目の前にある需要を満たす商品やサービスを開発・販売するだけがビジネスではありません。それら需要から生じる将来的なビジネスリスクを把握し、今後起こり得る需要を推定・対策を取る事で、競争の激しくないブルーオーシャン市場を早めに確保する事も可能となります。
3.競争や交渉を有利に運ぶ事ができる
また、他社・他人との競争や交渉を有利に運ぶことができるという理由もあります。業界や市場構造を把握していれば、ライバル企業含め、利害関係者を一通り知る事ができるからです。
したがって、それら情報を参考にして、自社ビジネスの収益性および実行可能性を高めることもできます。例えばその一つの方法として、動画の中でも言及しましたが、事業を合併したり、買収したりというM&Aのお話が出てきます。
4.他に知っておくとどんなメリットがあるのか?
他に、直接ビジネスやご自身のお仕事には関係がなくとも、間接的にメリットとなりうる場合があるので、ここでまとめてご紹介したいと思います。
まずは、金融業界や資本市場の知識を持っておく事で、国や社会を良くしていくための一助となりえる事です。日本は民主主義国家である以上、お金が市場でどのように流れているのか、どの分野に流れているのかを一人一人が理解していないと、適切な政治家を選び出すことは中々難しいと思います。
それに、大きな社会的ムーブメントとしていくためには、沢山のお金を持っている企業や資本家の協力が不可欠となります。最近ですと、LGBT推進運動が良い事例でしょう。大企業や資本家が、テレビや映画などのマスメディアを使って価値観の多様性推進に大きな役割を果たしたことは、欧米の情報に敏感な人であれば分かると思います。
個人の観点から見ても、マクロ的なビジネスの全体像を把握できるので、たとえ金融や財務のお仕事とは直接関係が無くとも、キャリアップという面でメリットになりうる場合があります。
後、私のような経営戦略コンサルタントの場合、金融業界やマーケットを知る事で、事業戦略を立てやすくなるという事情もあります。
5.まとめ
今回は以上となります。金融業界や資本市場の構造を知っておいた方が良い理由について論じてみました。
この記事では主にビジネス需要について書きましたが、他にも他社との競争時、取引相手との交渉時、世の中の改善、そして個人のキャリアアップなどでもメリットがあると分かりました。
このように考えていきますと、別に財務や金融のお仕事に就いていなくとも学んでおいた方が良いのでは?と私は感じます。たとえAIである程度答えを導き出せたとしても、どうやってその答えに辿り着いたのかを検証するためには、やはり専門知識は必要となるからです。
最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。
戦略コンサルタント
味水 隆廣
関連動画リンク:
『【集中講座2】財務知識の基本-ファイナンス業界のキャリアパスと資本市場』